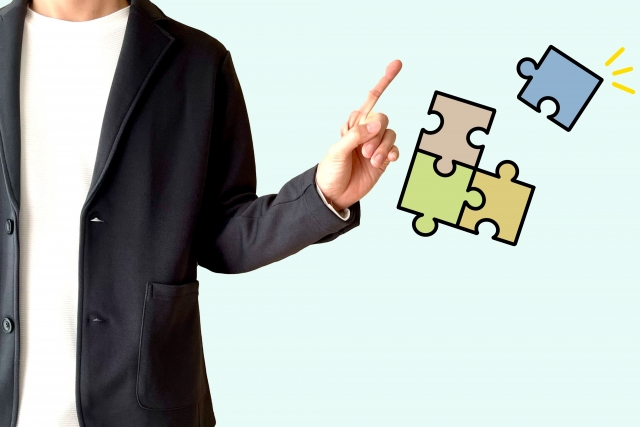【ビジネス用語解説】5W2Hとは?適切な使い方や例文をご紹介!
2025.07.22
ビジネスシーンでよく耳にする5W2Hですが、その意味や具体的な活用方法について、正しく理解できているでしょうか。5W2Hとは、情報を整理し、わかりやすく伝えるための基本的なフレームワークです。この考え方を習得することで、日々の業務におけるコミュニケーションの質を高め、プロジェクトを円滑に進めることが可能になります。この記事では、5W2Hの基本的な概念から具体的なビジネスでの応用例、そして他のフレームワークとの違いまで、体系的に解説します。ぜひ最後までご覧いただき、明日からのビジネスにお役立てください。
INDEX
5W2Hの概要
5W2Hは、ビジネスにおける情報整理や伝達に役立つフレームワークです。その意味や構成要素、そして似たフレームワークである5W1Hとの違いを知ることで、より効果的に活用できるようになります。また、これらの要素を効率的に覚える方法も存在します。まずは5W2Hの基本的な知識を押さえ、なぜビジネスにおいてこの考え方が重要視されるのかを理解していきましょう。ここでの基礎知識が、この後の具体的な活用方法の理解につながります。
5W2Hの基本的な意味と構成要素
5W2Hとは、情報を整理したり、相手にわかりやすく伝えたりするためのものです。
「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(なにを)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の5つのWと「Howmuch(いくらで)」の2つのHの頭文字を取ったもので「ご・だぶりゅー・に・えいち」と読みます。
これらの要素を明確にすることで、必要な情報の抜け漏れを防ぎ、関係者間での正確な情報共有を可能にすることが可能です。
例えば、業務の指示や報告、企画立案など、様々なビジネスシーンでそれらの考え方が活きます。
5W1Hと5W2Hの違い
5W1Hと5W2Hは、どちらもビジネスシーンで情報を整理・伝達するためのフレームワークですが、構成要素に違いがあります。
- 5W1H
「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(なにを)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の6つの要素で構成されたもの - 5W2H
5W1Hに「Howmuch(いくらで)」という要素が追加されたもの
上記のように「Howmuch」があることで、費用やコスト、数量など、金額や量に関する具体的な情報を盛り込むことができ、より詳細な情報整理や伝達が可能です。
5W2Hの効率的な覚え方
5W2Hの7つの要素を効率的に覚えるには、いくつかの方法があります。
一つは、それぞれの英単語の頭文字と意味をセットで繰り返し唱えることです。
When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、What(なにを)、Why(なぜ)、How(どのように)、Howmuch(いくらで)と声に出して覚えるのも効果的です。
また、それぞれの要素がどのような情報を指すのか、具体的な例をイメージしながら覚えるのも良いでしょう。
例えば「Whenは会議時間」「Whereは会議室」のように、実際のビジネスシーンに当てはめて考えることで、記憶に定着しやすくなります。
もちろん、情報のグループ分けとしてWhen・Where・Whoを状況設定、What・Howを出来事や行動、Why・HowMuchを理由や背景と捉える覚え方もおすすめ。
まずは使用する場面を想像しながら1つずつ覚えてみてはいかがでしょうか。
ビジネスで5W2Hが重要視される理由
ビジネスにおいて5W2Hが重要視される理由は、主にコミュニケーションの質を改善し、業務を円滑に進めるためです。
とりわけ、報連相(報告・連絡・相談)の精度向上に貢献します。
例えば、上司への報告の際に5W2Hを意識することで、「いつ、誰が、何を、なぜ、どのように行い、いくらかかったのか」といった必要な情報を網羅的に伝えることができ、説明不足を防ぐことが可能です。
5W2Hを意識することで、情報の受け手は状況を正確に把握しやすくなり、認識のずれや誤解を防げます。
結果として、手戻りや確認作業を抑え、業務効率の向上につなげられます。
また、自身の考えや依頼内容を伝える際にも、5W2Hを用いることで具体性が生まれ、相手に対しても正確な意図伝達が可能です。
5W2H活用の利点と課題
ここからは、5W2H活用の利点と課題について見ていきましょう。
5W2Hを使うことで得られる利点
5W2Hを活用することで得られる利点は多岐にわたります。
- 情報を論理的に整理する思考力が向上
⇒7つの要素に沿って考えることで、物事の全体像を把握し、必要な情報を網羅的に洗い出すことができる
⇒報告や連絡、相談の際に情報が不足したり、曖昧になったりすることを防げる - 相手にわかりやすく具体的に物事を伝えられるようになる
⇒コミュニケーションの質が向上し、認識のずれや誤解が減る
⇒口頭でのやり取りだけでなく、メールやチャット、報告書や企画書といったビジネス文書の作成においても同様 - 問題の原因分析や新しいアイデアの発想、プロジェクトの計画立案などのビジネスシーンで業務効率の向上や質の高い成果につながる
⇒具体的な数値を明確にするHowmuchの視点があるため、費用対効果を考慮した現実的な計画を立てやすくなる
5W2Hを使う上での課題
5W2Hは、いくつか注意すべき課題も存在します。
- すべての状況で7つの要素すべてを詳細に検討する必要があるわけではない
⇒状況によっては一部の要素に重点を置いた方が効果的な場合もある
⇒緊急性の高い報告ではまず結論(What)と理由(Why)、そして対応策(How)を簡潔に伝えることが求められる
⇒すべての要素を網羅しようとしすぎると、かえって情報過多になり、本当に伝えたいことが埋もれてしまう可能性もある - 分析することが目的となり、本来の目的を見失うリスクもゼロではない
- Howmuch(いくらで)の要素を深掘りしすぎると、時間や労力がかかる
5W2Hの活用事例と具体的な使い方
ここでは、5W2Hの活用事例と具体的な使い方について見ていきましょう。
業務指示や報告への応用
業務指示や報告において5W2Hを意識することで、情報の正確性と伝達効率を大幅に向上させることが可能です。
指示を出す側は「いつまでに(When)、誰が(Who)、どこで(Where)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)、いくらで(Howmuch)」を行うのかを明確に伝えることで、相手の理解を深め、手戻りを防ぎます。
例えば「来週月曜日の午前中に(When)、Aさんに(Who)、3階会議室で(Where)、〇〇プロジェクトに関する資料作成を(What)、次回会議での説明に必要なので(Why)、過去のデータを参考にしながら(How)、〇円の予算内で(Howmuch)行ってほしい」といった具体的な指示は、受け手にとってわかりやすいです。
報告の際も同様に、上記の要素を含めることで、状況や結果を網羅的に伝えることができ、議事録や報告書の作成時にも情報の抜け漏れを防ぐことができます。
具体的な例文としては、「本日15時に(When)、私が(Who)、B社で(Where)、新製品の提案を行い(What)、顧客の課題解決のため(Why)、製品デモを用いて(How)、〇円の見積もりを提示しました(Howmuch)」などが考えられるでしょう。
目標設定における活用
目標設定においても、5W2Hは有効なツールです。
漠然とした目標ではなく、より具体的で達成可能な目標を設定するために、各要素を明確にしていきます。
「なぜ(Why)この目標を達成する必要があるのか」という目的を明確にすることから始め、その上で「何を(What)達成するのか」、「いつまでに(When)」、それは「誰が(Who)」担当し、「どこで(Where)」行うのかを定めます。
加えて「どのように(How)」目標を達成するための具体的な方法やステップを検討し、「達成するためにどれくらいのコストがかかるのか(Howmuch)」も考慮に入れることで、より現実的で実行可能な目標を設定することが可能です。
例えば「顧客満足度を向上させるため(Why)次回アンケートで満足度80%を達成する(What)、半年後までに(When)私が中心となりチームで(Who)、オンラインと対面の両方で(Where)、顧客ヒアリングや改善活動を行い(How)、必要なツール導入に〇円をかける(Howmuch)」といったように、5W2Hのフレームワークを用いることで、目標が明確になり、達成に向けた具体的な行動計画を立てやすくなるのではないでしょうか。
プレゼンテーションでの活用
プレゼンテーションは聞き手に何かを伝え、理解や共感を得て行動を促すためのものです。
ここで5W2Hを活用すると、話の構成が明確になり、聞き手にとって非常にわかりやすいプレゼンテーションを行うことができます。
- 「なぜ(Why)この話を聴く必要があるのか」という目的や重要性を最初に伝えることで、聞き手の関心を引く
- 「何を(What)について話すのか」というテーマや内容を示し、「誰に(Who)向けた話なのか」、「いつ(When)の話なのか」、「どこで(Where)起こったこと・行うことなのか」といった背景情報を提供する
- 「どのように(How)」それを実現するのか、具体的な方法やプロセスを説明する
- 「どれくらいの費用がかかるのか(Howmuch)」や得られる成果などを数字で示すことで、提案の具体性や妥当性を補強する
上記のように、5W2Hの要素を意識してプレゼンテーションを構成することで、論理的で説得力のある話を展開可能です。
プレゼンテーションが苦手な人も、一度5W2Hを意識することで構成がわかりやすくなり、自分自身も安心して進行できるようになります。
事業計画への適用
事業計画の策定は、ビジネスを成功に導くために不可欠なプロセスです。
5W2Hは、事業計画を具体的に検討するための強力なフレームワークとなります。
- 「なぜ(Why)この事業を行うのか」という事業の目的やビジョンを明確する
- 次に、「何を(What)提供する事業なのか」、つまり商品やサービスの内容を具体的に定義する
- 「誰を(Who)ターゲットとするのか」、「いつ(When)事業を開始し、どのようなスケジュールで進めるのか」、「どこで(Where)事業を展開するのか」といった基本的な要素を定める
- 「どのように(How)事業を運営していくのか」、具体的なビジネスモデルや戦略を検討し、「事業を開始・継続するためにいくら(Howmuch)の資金が必要なのか、どのような収益構造を目指すのか」といった財務的な側面も詳細に計画に盛り込む
上記のように5W2Hに沿って検討を進めることで、事業の全体像が明確になり、実現可能性のある計画を立てることができるでしょう。
まずは5W2Hを意識しつつ、事業計画を進めてみてはいかがでしょうか。
マーケティング戦略での応用
マーケティング戦略の立案においても、5W2Hは有効です。
市場や顧客を深く理解し、効果的な戦略を構築するために、各要素を丁寧に分析します。
- 「なぜ(Why)マーケティング活動を行うのか」という目的、例えばブランド認知度向上や売上拡大などを明確にする
- 「何を(What)マーケティングの対象とするのか」、具体的な商品やサービスを特定する
- 「誰に(Who)向けて行うのか」、ターゲット顧客やペルソナを詳細に設定する
- 「いつ(When)実施するのか」、キャンペーン期間やプロモーションのタイミングを計画し、「どこで(Where)情報を届けるのか」、オンライン広告、SNS、イベントなど、チャネルを選択する
- 「どのように(How)ターゲットにアプローチするのか」、具体的な施策やクリエイティブを検討し、「どれくらいの費用(Howmuch)をかけるのか」、予算を設定する
上記のように5W2Hを用いることで、ターゲット、メッセージ、タイミング、チャネル、コストといったマーケティング戦略の重要な要素を網羅的に検討し、より効果的な施策を立案できるでしょう。
企画書の作成に役立てる
企画書は、新しいアイデアやプロジェクトの承認を得るために、内容や目的、実現可能性などをわかりやすく伝えるための重要な書類です。
企画書の作成に5W2Hを取り入れることで、網羅的で説得力のある企画書を作成することができます。
- 企画の「目的(Why)」や「概要(What)」を明確に提示し、「誰が(Who)」主体となって行うのか、「いつまでに(When)」、そして「どこで(Where)」実施するのかといった基本的な情報を整理する
- 企画を「どのように(How)」進めるのか、具体的な方法論やスケジュールを示す
- 最後に企画に「いくら(Howmuch)」の費用がかかるのか、期待される効果や収益はどの程度かといったコストとリターンの側面を明確にする
上記のように5W2Hを用いることで、企画の実現可能性や妥当性を効果的に伝えることができるのではないでしょうか。
議事録や報告書への活用
議事録や報告書は、会議の内容や業務の進捗、結果などを正確に記録し、関係者間で共有するための重要な文書です。
これらの書類を作成する際に5W2Hを活用すると、情報の抜け漏れを防ぎ、後から見返した際にも内容を素早く正確に把握できるようになります。
議事録であれば、「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」参加して、「何を(What)」話し合い、「なぜ(Why)」そのような決定に至り、「どのように(How)」今後進めることになったのか、そして関連する「費用(Howmuch)」はどのくらいか、といった要素を盛り込むことで、会議の経緯や決定事項を網羅的に記録できます。
報告書の場合も、「いつ(When)」「誰が(Who)」何について「何を(What)」行い、「なぜ(Why)」そのような結果になり、「どのように(How)」進めていくのか、そして関連する「費用(Howmuch)」は、といった視点で記述することで、状況を的確に伝えることが可能です。
5W2Hを使う際の効果的な方法
次に、5W2Hを使う際の効果的な方法について見ていきましょう。
情報を整理するためのメモ活用
5W2Hを使って情報を整理する際には、メモを活用することが効果的です。
頭の中で漠然と考えているだけでは情報が整理されず、抜け漏れが生じる可能性があります。
そこで、紙やデジタルツールを使って、5W2Hの各要素を書き出し、それぞれの項目に該当する情報を具体的に書き込んでいくのです。
このプロセスを通じて、思考が可視化され、どの部分の情報が不足しているのか、あるいはどの部分をもっと深掘りする必要があるのかが明確になります。
会議中に議事録を取る際にも、あらかじめ5W2Hのフレームでメモを取るようにすると、効率的に要点を押さえることが可能です。
また、新しいアイデアを検討する時にも、5W2Hに沿って要素を書き出すことで、アイデアを具体化し、実現に向けた課題や必要な情報を見つけやすくなります。
状況に応じた質問の順番の工夫
5W2Hの要素には一般的な順番がありますが、ビジネスの状況や目的に応じて、質問の順番を工夫することが効果的です。
例えば、問題解決に取り組む際には、「なぜ(Why)」その問題が発生したのか、原因を深掘りすることから始めるのが有効となります。
目的や理由が明確になることで、その後の「何を(What)」すべきか、「どのように(How)」進めるべきかといった具体的な行動が見えてくるでしょう。
また、企画提案を行う場合は「なぜ(Why)」その企画が必要なのか、その背景や目的を最初に伝えることで、聞き手の関心を惹きつけ、その後の内容を理解しやすくすることができるのではないでしょうか。
このように、伝えたい情報の重要度や、聞き手が何を求めているのかを考慮して質問の順番を調整することで、より効果的なコミュニケーションや思考整理が可能になります。
必ずしもWhenから始める必要はなく、柔軟に順番を入れ替えて活用することが肝心です。
必要に応じた追加の視点
5W2Hは汎用性のあるフレームワークですが、ビジネスの複雑な状況に対応するためには、必要に応じて追加の視点を持つことも有効です。
例えば、マーケティング戦略を検討する際には、4P分析(Product,Price,Place,Promotion)や顧客の心理プロセス(AIDMAなど)といった他のフレームワークと組み合わせることで、より多角的に状況を分析し、戦略を立案することが可能です。
また、プロジェクト管理においては、リスク管理や品質管理といった視点を加えることで、より実践的な計画を立てることが可能になります。
5W2Hはあくまで基本的な骨組みであり、特定の分野や状況に特化した詳細な情報を補うためには、その分野特有の専門的な視点や分析手法を取り入れることが効果的と言えます。
5W2H以外のビジネスフレームワーク
最後に、5W2H以外のビジネスフレームワークについて見ていきましょう。
5W1H
5W1Hは、5W2Hの基となるフレームワークであり、「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(なにを)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の6つの要素で構成されます。
これは情報を整理したり、物事をわかりやすく伝えたりするための最も基本的なフレームワークです。
ビジネスにおける報連相や業務指示など、日常的なコミュニケーションにおいて、情報の抜け漏れを防ぎ、相手に意図を正確に伝えるために広く活用されています。
5W2Hは、この5W1Hに「Howmuch(いくらで)」という費用や量に関する視点を加えることで、より具体的な数値情報を含めた議論や計画を可能とするものです。
5W3H
5W3Hは、5W2Hにさらに要素を追加して情報をより詳細に整理するためのものです。
5W2Hの7つの要素に加えて、「Howmany(どのくらい、いくつ)」が加わったものを指すのが一般的とされています。
Howmanyが加わることで、数量や回数といった具体的な数値情報をさらに詳細に把握することが可能になり、生産計画や販売計画など、量的な要素が重要なビジネスシーンに活用できます。
ただ、要素が増える分、すべての項目を埋めようとすると情報収集や整理に時間がかかるので、必要な要素を選択して活用することが鍵です。
6W2H
6W2Hは、5W2Hの要素に加えて「Whom(誰に)」という視点を明確にしたものです。
5W2HのWhoは「誰が」「誰に」の両方を意味することがありますが、6W2Hではこれを「Who(誰が)」行うのか、「Whom(誰に)」向けて行うのかを分けて考えます。
これにより、行動の主体と対象をより明確に区別することができ、顧客や特定の関係者へのアプローチが必要なマーケティングや営業戦略に活用できます。
とりわけ、ターゲット顧客をより具体的に設定したい場合などに有効なフレームワークです。
PREP法
PREP法は、主に文章構成やプレゼンテーションの際に役立つフレームワークで、情報をわかりやすく論理的に伝えるための手法です。
PREPは「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(再度結論)」の頭文字を取っています。
まず結論を述べ、次にその理由を説明し、具体的な例を挙げて内容を補強し、最後に改めて結論を繰り返すという流れで構成されます。
それにより、聞き手は話の要点を最初に把握し、その後の説明で理解を深めることが可能です。
5W2Hは情報を網羅的に整理することに長けているのに対し、PREP法は情報をわかりやすく伝える構成を作ることに特化していると言えるでしょう。
したがって、5W2Hで整理した情報をPREP法を用いて効果的に伝えるというように、組み合わせて活用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
ここまで、5W2Hの基本的な意味からビジネスでの具体的な活用方法、そして関連する他のフレームワークについて解説してきました。
5W2Hは「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(なにを)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」「Howmuch(いくらで)」の7つの要素で情報を整理する方法であり、適切に活用することで、コミュニケーションの精度向上、業務効率化、問題解決、企画立案など、ビジネスの多種多様な場面に活用できます。
これらは単に技術や知識として知っているだけでなく、日々の業務の中で意識的に活用し、情報を整理したり、相手に伝えたりする習慣を身につけることが大切です。
最初はすべての要素を網羅しようとせず、まずはそれぞれWhy(なぜ)やWhat(何を)など重要となる要素から考え始めるのが良いでしょう。
また、状況に応じて要素の順番を入れ替えたり、他のフレームワークと組み合わせたりすることで、より効果的な活用が可能となるのではないでしょうか。