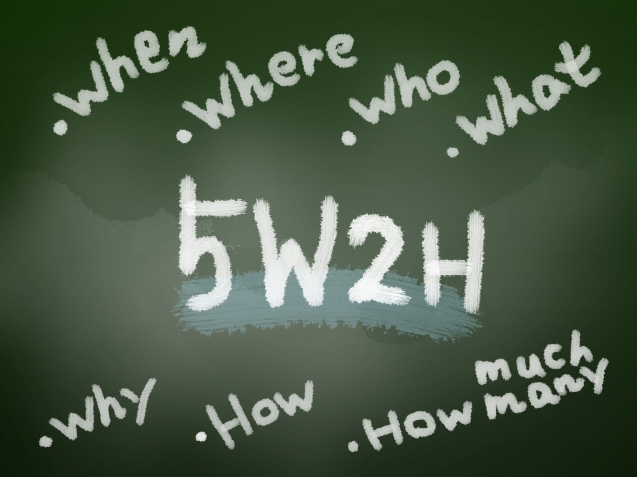CPF(カスタマープロブレムフィット)とは?
2025.07.01
CPF(カスタマープロブレムフィット)は、顧客の課題が存在するかどうかはもちろん、課題に対して提供しようとしている製品やサービスが的確な解決策となるかを検証するプロセスもしくは検証された状態を表す言葉です。
ただ、上記の説明を受けても具体的にイメージしにくいかもしれません。
そこで、この記事では、CPFの定義と目的と重要性、主な活動、関連する概念、広告・マーケティングにおけるCPFについて詳しく解説します。
INDEX
CPFの定義と目的と重要性
まずは、CPFの定義と目的と重要性について見ていきましょう。
CPFとは
CPFは「CustomerProblemFit」の略で、顧客の課題が存在するか、課題に対して提供しようとしている製品やサービスが的確な解決策となるかを検証するプロセスもしくは検証された状態を指す言葉です。
さらに噛み砕いて表現すると、『「顧客が本当に抱えている重要な問題に、自社のサービスや製品がドンピシャで合っている状態」』のことを指します。
スタートアップ(新規事業の立ち上げ)において、顧客が抱える問題やニーズが実際に存在し、かつ解決するに値するかを見極めるためのステップとなります。
CPFの目的
CPFは、顧客が抱える課題について仮説検証を行い、顧客イメージや顧客が持つ課題と要因、課題を解決する方法などを明確にするのが主な目的です。
顧客との対話を通じてフィードバックや意見を集め、顧客が本当に求めているものを理解し、製品やサービス開発の方向性を見極めることが求められます。
CPFの重要性
CPFは、スタートアップ(新規事業)を成功に導くための基盤となります。
誰のどのような課題を解決するのかを明確にしないままプロダクト開発を進めてしまうと、ビジネスが失敗に終わることも珍しくありません。
逆にCPFによって顧客のニーズや課題を正確に把握し、それに合致したプロダクトを提供することで、真の価値提供への道筋を明らかにすることが可能です。
ビジネスのアイデアの初期段階でCPFを検証し、必要に応じて修正を行っておいて損はありません。
また、CPFは無駄な開発コスト削減にも繋がります。
ゆえに、定期的な見直しを行うのが理想です。
CPFの進め方
次に、CPFの進め方について見ていきましょう。
CPFを進める流れ
CPFは、以下のようないくつかのステップを経て進められます。
- 対象となる顧客像を明確にする「ペルソナ設定」を行う
- 設定したペルソナがどのような行動をするか「顧客の行動分析」を行う
- 分析結果をもとに顧客が製品やサービスに接触するまでのプロセスを可視化する「カスタマージャーニー設定」を行う
- 途中の過程で明らかになった情報を整理して課題解決の「条件整理」を行う
以上のステップを踏むことで、CPFを効率的に進めることが可能です。
具体的な「ペルソナ設定」「顧客の行動分析」「カスタマージャーニー設定」「条件整理」については、次の項目を参考にしてみてください。
ペルソナ設定
ペルソナ設定は、CPFの最初の重要なステップです。
これは、ターゲットとなる顧客の典型的な人物像を詳細に定義する作業となります。
具体的には、単に年齢や性別だけでなく、職業、収入、居住地、家族構成といったデモグラフィック情報に加え、興味・関心、価値観、ライフスタイル、何に悩み、どのような課題を抱えているかといった心理的な側面まで深く掘り下げて設定するのがコツです。
ペルソナを具体的に設定することで、顧客に対する理解が深まり、その後の課題分析やカスタマージャーニー作成の精度をアップさせられます。
顧客の行動分析
ペルソナ設定で定義した顧客像に基づき、顧客がどのような状況で、どのような情報に触れ、どのように購買やサービス利用に至るのか、一連の行動を分析します。
オンラインでの検索行動、SNSでの情報収集、店舗への来店、他者のレビュー参照など、顧客が製品やサービスと接点を持つ可能性のあるあらゆる行動を洗い出し、背景にある意図や感情を理解することが重要です。
この分析を通じて、顧客が課題に直面する具体的な状況やその際に取るであろう行動を把握することで、後のカスタマージャーニー作成や課題検証がスムーズに進むでしょう。
カスタマージャーニー設定
顧客の行動分析で得られた知見をもとに、顧客が製品やサービスを知って興味を持ち、購入または利用に至り、最終的に情報発信を行うまでの一連のプロセスを時系列で可視化するのがカスタマージャーニー設定です。
この段階では、各フェーズにおいて顧客がどのような感情を持ち、どのような疑問や課題に直面するのかを詳細に描写します。
それにより、顧客視点での課題やニーズが明確になり、どの段階でどのようなアプローチが効果的かを検討するための重要な示唆が得られます。
大切なのは、詳細に項目を設定することです。
条件整理
ペルソナ設定、顧客の行動分析、カスタマージャーニー設定を通じて顧客の課題やニーズが明らかになったら、それを取り巻く環境や制約条件などを整理します。
具体的には、これらの顧客が抱える課題は本当に解決に値する深刻なものか、課題を解決するために顧客はどのような手段をとっているか、競合となる代替手段は何か、課題解決に対する顧客の支払い意欲はどの程度かといった点を明確にすると良いです。
上記の条件を整理することで、提供しようとしている解決策が顧客の課題に対して本当にフィットするのかを評価するための準備が整うでしょう。
まずは、ステップごとに1つずつ実践してみてはいかがでしょうか。
CPFでの主な活動
ここからは、CPFでの主な活動について見ていきましょう。
顧客インタビュー
CPFにおいて、顧客インタビューは最も重要な活動の一つです。
インタビューを通じて、設定したペルソナが実際にどのような課題を抱えているのか、課題はどれほど深刻なのか、課題解決のためにお金を払う意欲があるのかを直接的に把握することができます。
顧客の日常やビジネスにおける具体的な状況について質問し、課題が彼らにどのような影響を与えているのかを深く理解することが大切です。
また、課題解決に対する価値観や、現在代替手段として利用しているものについても尋ねることで、顧客の隠れたニーズや満たされていない要望を引き出すことができます。
バーニングニーズの検証
バーニングニーズとは「髪の毛に火が付いている」ように、顧客が緊急かつ切実に解決を求めている課題を指します。
みなさんも、喫緊の問題に対しては「すぐに解決したい」と思うはず。
CPFでは、顧客インタビューなどを通じて、このようなバーニングニーズが存在するかどうかを検証するのが一般的です。
基本的に顧客はバーニングニーズを解決できる製品やサービスに対しては、お金を支払う意欲を持っている傾向にあります。
もし、顧客が抱える課題が表面的なものであったり、切実さがなかったりする場合は、ターゲットとする課題や顧客を変えるといった見直しが必要です。
課題の質の向上
CPFの目的の一つは、顧客が抱える課題の質を向上させることにあります。
表面的な課題だけでなく、顧客自身も気づいていないような潜在的な問題や、より根本的な問題を発見し、検証することが求められるわけです。
そのためには顧客との対話を深め、共感的な姿勢で耳を傾けることで、顧客の行動や発言の裏にある真のニーズや不満を見つけ出す必要があるでしょう。
このように課題の質を向上させることで、より不特定多数の顧客に価値を提供できる可能性が生まれ、事業展開にも繋げられるのではないでしょうか。
CPFと関連する概念
ここでは、CPFと関連する概念について見ていきましょう。
フィットジャーニーにおけるCPFの位置づけ
フィットジャーニーとは、事業アイデアの立案から特定の市場への適合、成長に至るまでの道のりを示す概念です。
CPFは、これらフィットジャーニーの最初の段階に位置づけられます。
それらのフェーズでは「顧客の課題が存在するかどうか」を検証し、顧客の抱える課題を正しく理解することが不可欠です。
そのための最初のステップがCPFとなります。
この後、PSF(プロブレムソリューションフィット)、SPF(ソリューションプロダクトフィット)、PMF(プロダクトマーケットフィット)といった段階へと進んでいくので、後の項目もあわせて参考にしてみてください。
PSF(プロブレムソリューションフィット)
PSFは「ProblemSolutionFit」の略で、顧客が抱える課題(Problem)に対する解決策(Solution)が適切であるかを検証する段階です。
CPFで顧客の課題が明確になった後に取り組むフェーズであり、提案する解決策が本当に顧客の課題を解決できるのか、顧客はその解決策を受け入れるのかを検証します。
この段階では、プロトタイプの提示やデモンストレーションなどを通じて、顧客の反応を見ながら解決策の有効性を評価します。
最終的にPSFが達成されると、顧客の課題に対して有効な解決策が見つかった状態と言えるでしょう。
PMF(プロダクトマーケットフィット)
PMFは「ProductMarketFit」の略で、開発した製品やサービス(Product)が特定の市場(Market)に適合している状態を言います。
CPFとPSFを経て、顧客の課題に対する有効な解決策を持つプロダクトが開発された後に目指す最終的なフィットの状態です。
例外こそあるものの、PMFが達成されると幅広い顧客に受け入れられ、継続的に利用されるようになり、事業が持続的に成長する基盤ができます。
CPF・PSF・PMFは密接に関連しており、CPFで顧客の課題を深く理解することが、後のPSF、そして最終的なPMF達成のために不可欠となるわけです。
広告・マーケティングにおけるCPF
最後に、広告・マーケティングにおけるCPFについて見ていきましょう。
SNS広告のCPF
SNS広告におけるCPFは「CostPerFollow」の略称として使用されます。
プラットフォーム上で広告を配信し、ユーザーが広告を通じて企業やブランドのアカウントをフォローまたは友達追加、いいねするごとに発生する広告費用単価を意味します。
例えば、X(旧Twitter)やInstagramではCostPerFollow、LINEではCostPerFriend、FacebookではCostPerFanと呼ばれますが、いずれも同様にフォロワーや友達、ファンの獲得にかかる費用の指標として使用されるのが一般的です。
基本的にSNSアカウントのフォロワー数を獲得したい場合に、広告の効果測定や費用対効果の評価などで使用するものです。
SNS広告におけるCPFの重要性
SNS広告において、CPFはマーケティング戦略を評価する上で重要な指標の一つです。
CPFを把握することで、広告の効果を数値的に評価し、どの広告や施策が効率的にフォロワーを獲得できているのかを判断できます。
CPFを改善し、より低いコストでフォロワーを獲得できるようになれば、限られた広告予算をより効果的に活用することが可能となるでしょう。
なお、獲得したフォロワーは、後の継続的なコミュニケーションやエンゲージメントに繋がり、最終的なコンバージョンや売上向上に貢献する可能性も……。
もし広告での有効性に問題がある場合、継続的に改善するところから着手してみてはいかがでしょうか。
まとめ
本記事では、CPFの定義と目的と重要性、主な活動、関連する概念、広告・マーケティングにおけるCPFについて詳しく解説しました。
CPFは、新規事業やプロダクト開発において、顧客の本当の課題を深く理解し、課題解決に焦点を当てることで、事業成功の可能性を高めるための考え方です。
また、SNS広告においては、フォロワー獲得単価として活用されることもあります。
CPFを理解して実践すれば、顧客視点に基づいたより効率的な事業戦略やマーケティング施策を展開できるようになるでしょう。
まずは、日々のビジネス活動にCPFの視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。